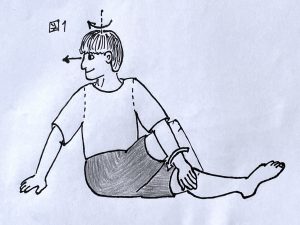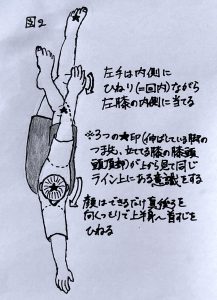YouTubeを開くと、久しぶりにAMBITIOUS JAPAN!の文字が。
YouTubeのトップページでは、往々にしてその時の時事に因んだ動画が現れますが、昨年11月にこのTOKIOのAMBITIOUS JAPAN!の動画が出て来ました。
AMBITIOUS JAPAN!(アンビシャス ジャパン!)
東京駅と新大阪駅を走るJR東海の東海道新幹線で列車の発着時の車内放送に、メロディの一部がかつて使われていた楽曲で、男性バンドグループTOKIOの2003年発表の曲です。

現代の「鉄道唱歌(明治期の鉄道の普及に伴い、沿線の街の名前を織り込んで作られた愛唱歌、一番「きーてきいっせいしんばしをー…」の出だしが有名)」をとのJR東海社長の依頼で、昭和の歌謡曲を多数書かれたなかにし礼作詞、ポップスやアイドルの曲を多数書かれた筒美京平作曲の楽曲で、JR東海のキャンペーンソングとして制作されTOKIOに提供されました。
旅ゆく人の気持ちとその旅ゆく友へのはなむけの言葉で構成された歌ですが、旅のワクワク感やまた新幹線の躍動感が非常に感じられる歌で、まさに現代の鉄道愛唱歌にふさわしい歌だとしみじみ思い直しました。
当然好評で予定より長らく車内放送で使われていましたか、2023に他の曲に代えられ惜しまれながら車内放送からは引退しました。
これがきっかけであらためてTOKIOの楽曲について考察してみました。
これはメインボーカルの長瀬さんの歌い方の為だと思いますが、なんというかどの曲も「魂の叫び」をすごく感じます。なんかメッセージが「こころに刺さる」感じがして、同じジャニーズながらSMAPの歌の、こちらは基本皆で順繰りに歌唱して「こころに染み込んでくる」感じとはまた違って、こちらはこちらでなんかいいんですよね。
あとドラム
ドラムマシーンの如く正確精密なドラミングでは、亡くなられたYMOの高橋幸宏さんが一番だと思ってますが、TOKIOの松岡さんのドラミングは「スティックがドラムの上で踊り跳ねてる」感がすごく感じて、こちらはこちらでロックのドラム感で味があります。
今回の投稿にあたり、TOKIOの20周年ベストアルバム「HEART」(これも2014と一昔前!)を取り寄せて聴いてみたのですが、
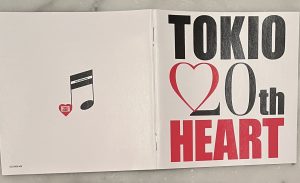
歌詞を読み上げるといかにもアイドル曲然ながらも、夏フェス(2014のサマーソニック)参加時には、この曲で会場めちゃくちゃ盛り上がったと聞き、見直してしまったデビュー曲の
「LOVE YOU ONLY」 2014サマソニのライブ映像
長瀬さんがチーマーあがりの研修医という、よく考えるとめちゃくちゃな設定ながら実は自分結構よくみていたドラマ「ハンドク(半人前のドクターという意味)」の主題歌
「DR」
長瀬さんの編曲への関与で、原曲よりかなりTOKIOらしくなってるといわれていますが、それでも私は作詞作曲の中島みゆき節炸裂かなと思ってる
「宙船(そらふね)」
当時よく耳にしまた時には口にした歌が、なんか大仰な表現ですが走馬灯の様に思いだされます。
私は午後に往診に行くのですが、患者さんのお宅についているテレビで、昼下がりの情報番組でリーダー城島さんの出演を最近よくお見かけします。
TOKIOの多くの楽曲の作詞作曲編曲に携わってきたとされる城島さんが、番組内の通販コーナーでとはいえ通販商品の褒め倒し?している姿を見るとなんだか複雑な気持ちですが、TOKIOのメンバー各人各々いま出来ることを頑張っておられるのかと納得するようにしています。
解散の原因となった山口さんが、自身が経験したアルコール依存症の講演で引っ張りだこと今話題になっています。
解散の原因は他のことが主因のくせにアルコール依存症を前面に出してええ格好しやがって、また講演しまくりで荒稼ぎしやがってけしからんというような論調のネット上の意見も散見しますが。
いやいやアルコール依存症、古くからあり決して今に始まったことトレンドではないものの、数ある社会問題のなかでは上位に入る課題だと思います。それを知名度のある方が自身の体験を語り問題提起してゆくことは立派な社会貢献のひとつではないでしょうか。講演による啓蒙活動が贖罪となっていると、部外者である我々は見守るべきことではないかなと思います。
数年前に、同じジャニーズの男闘呼組の約30年ぶりの復活が話題になりました。
解散の経緯はそちらと異なり、山口さんの場合個人の相手の在る事項が原因ゆえクリアとなるには相当困難かもしれません。また久しぶりのAMBITIOUS JAPAN!視聴のきっかけとなった国分さんの件も、報道で知る限りでは我々第三者にはいったい何があったのかさっぱりよくわからないままですが、将来どうにか解決して、5人で演奏歌唱する姿を直に見られる日がまたいつか来ればと願って止みません。